日本水難救済会神奈川県支部大磯救難所
大磯町は神奈川県の県中央南部に位置しており相模湾に面し冬でも温暖な気候で晴天時には大島・三浦半島・箱根連山そして富士山が一望できる自然環境に恵まれた町である。また大磯といえば全国で始めての海水浴場発祥地としても有名であり、明治18年当時陸軍軍医松本順氏により病気療養と健康増進のため提唱されたと当時の記録に示されており現在も海水浴シーズン(7月・8月)には家族ずれを中心に約40万人が当地を利用しております。
さて、当救難所は日本水難救済神奈川県支部の配下にあり救難艇第三こゆるぎ丸12トンを所有、緊急時には出動し救助活動を行っている所であります。
相模湾西部地区には同様の救難所が当救難所を含め4救難所ありそれぞれの地区で救助活動を行っております。当救難所は平塚海岸より二宮海岸までを担当し海難事故発生時の出動体制を整えておりますが、大磯町漁業協同組合の組合員により組織されており各漁業操業の傍ら救助活動を行っておりますので事故発生時の救助退院の確保が難しい面もありますが人命にかかわることですので発生時には率先して救助活動に携わっていただいております。
先日も、平塚海岸でサーファーが高波にのまれあわや人命が奪われるかもしれない事故が発生しました。これは、18歳のフリーターで早朝自宅を出て(埼玉県)途中仮眠とコンビニで軽食をとり午前7時ごろ平塚海岸につきサーフィンを友人2人と行っていたが友人2人は途中で引き揚げ休憩をしていたが同氏は引き続き行っていた模様ですが時間が大分経過し友人が様子を見にいったところ
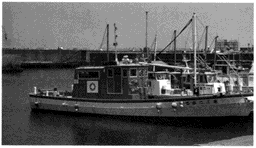
救難艇第三こゆるぎ丸
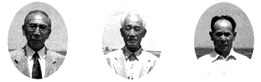
写真左より救難所顧問大磯町漁業協同組合代表理事組合長・真間直次氏、救難所所長・渡辺秀雄氏、救難所副所長・真間次男氏。
高波に揉まれており、すぐに消防署に連絡救助を求め、当救難所へ出動依頼があった。しかし組合員の大半が操業に出ておりたまたま早朝の操業から戻った組合員数人が自宅で仮眠をとっていたので出動を依頼し救助に向かった。救助されたときは精も根も尽き果てた状態で後数分遅れれば助からなかったかもしれないと思われた事故であった。
いずれにしても、このような事故は一人一人がその場の状況と体調を良く判断し行動していれば起こらなかったと思われる。海での事故は一刻を争う場合が多く二重遭難の危険性が伴うため救助に出動できないこともしばしばある。一人のために多くの人及び関係機関にも多大な迷惑が係る事を認識してもらいたい。
サマーレジャーが本格的になってくる季節に向かい我々救助所隊員一同海難事故がないことを願ってやまない。
救難所別救助実績(S48.4.1〜H8.3)
|
項目 救難所 |
出動した |
救助した |
| 回数 |
船 |
人数 |
船 |
人数 |
| 柴 |
5 |
23 |
56 |
1 |
22 |
| 横須賀 |
37 |
244 |
604 |
19 |
85 |
| 走水大津 |
78 |
179 |
683 |
49 |
151 |
| 鴨居 |
61 |
197 |
664 |
39 |
78 |
| 久里浜 |
38 |
175 |
767 |
26 |
79 |
| 北下浦 |
59 |
82 |
313 |
27 |
71 |
| 南下浦 |
16 |
97 |
269 |
16 |
23 |
| 三浦 |
39 |
225 |
677 |
23 |
57 |
| 長井 |
22 |
68 |
427 |
14 |
41 |
| 大楠 |
23 |
34 |
265 |
14 |
29 |
| 腰越 |
19 |
27 |
91 |
12 |
24 |
| 大磯 |
94 |
148 |
664 |
31 |
64 |
| 小田原 |
45 |
70 |
285 |
13 |
56 |
| 真鶴 |
42 |
78 |
439 |
18 |
69 |
| 観音崎 |
35 |
41 |
111 |
31 |
126 |
| 二宮(支所) |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
| 計 |
614 |
1,689 |
6,316 |
333 |
976 |
前ページ 目次へ 次ページ